2025年度第3回(9月28日)
我孫子市谷津ミュージアム(岡発戸・都部谷津)
自然まるごと観察会
後援:我孫子市 主催:NPO法人自然観察大学

私たち自然観察大学では、生きものの名前を知るだけではなく、
その形を見て、くらしを考えます。
さらに生き物どうしの関わり、とりまく環境に注目して観察していきます。
植物、鳥、虫、きのこなどいろいろな角度から、
専門家と参加者のみなさんとが一緒になって観察します。
観察フィールは我孫子市の谷津ミュージアム(岡発戸・都部谷津)。
地元のみなさんの活動によって、自然豊かな里山環境が保たれています。
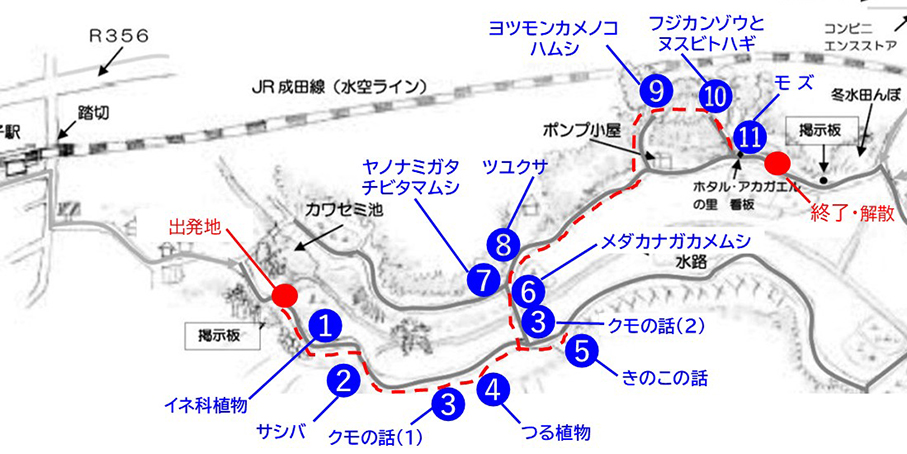
当日の観察ルート(我孫子市HPより改変)
その形を見て、くらしを考えます。
さらに生き物どうしの関わり、とりまく環境に注目して観察していきます。
植物、鳥、虫、きのこなどいろいろな角度から、
専門家と参加者のみなさんとが一緒になって観察します。
観察フィールは我孫子市の谷津ミュージアム(岡発戸・都部谷津)。
地元のみなさんの活動によって、自然豊かな里山環境が保たれています。
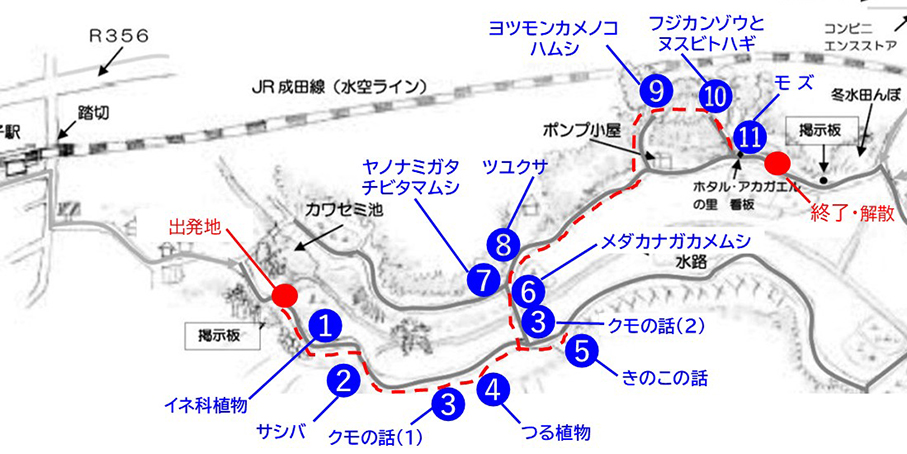
観察会の話題の概要
詳しい内容はそれぞれのタイトルのあとのリンク(⇒)をご覧ください(PDF)
レポートの全体(PDF)を通読するには次をクリックしてください ⇒

|
【イネ科植物をくらべてみよう】(⇒) |
|
|---|---|---|
 |
【サシバの生活について】(⇒) |
|
 |
【クモの生態観察】(⇒) |
|
 |
【つる植物をくらべてみよう】(⇒) |
|
 |
【きのこの観察】(⇒) |
|
 |
【メダカナガカメムシの観察】(⇒) |
|
|
|
【ヤノナミガタチビタマムシの観察】(⇒) |
|
 |
【ツユクサの花のつくり】(⇒) |
|
 |
【ヨツモンカメノコハムシの観察】(⇒) |
|
|
|
【フジカンゾウとヌスビトハギをくらべる】(⇒) |
|
|
|
【モズが減っている原因】(⇒) |
|
 |
【そのほか話題になったものなど】(⇒) |
|
参加いただいたみなさん、担当講師、スタッフのみなさん、ありがとうございました。 |
||
| 各講師のプロフィールはこちらからご覧ください ⇒ |
||
2026年度の自然まるごと観察会は、2026年3月ころに募集開始の予定です |
| ほかの記事 | このほかの観察会レポートは次でご覧いただけます | ⇒ |
|---|
